どうもこんにちは、えるやんです。
今日はバーベキューをする時に、何気なく利用している炭のお話。
実は、炭とひとことで言っても様々な種類があり、火のつきやすさや燃焼時間など、炭ごとに様々な特徴があります。
今回は、バーベキュー歴10年の僕が炭の中でもメジャーな4種類をピックアップして、それぞれの特徴を解説して独断と偏見でオススメの炭をご紹介します。
また、簡単で失敗しない火起こしもご紹介するので最後まで見てもらえると嬉しいです!
この記事を読むと
- 炭の種類と特徴がわかる
- オススメの炭がわかる。
- 失敗しない簡単な火起こしができる。

メジャーな炭4種類をご紹介
それでは早速、主な炭の種類は下記の4種類をご紹介。
ここで覚えて売り場でどの炭を買えばいいか迷わないようにしておきましょう!
- マングローブ炭
- 黒炭
- 白炭
- オガ成形炭
個人的にはオガ成形炭の一種【オガ炭備長炭】をオススメしています。
 えるやん
えるやんオガ炭備長炭は火付きは悪いけど、値段と燃焼時間を考えると高コスパ!
マングローブ炭
ホームセンターでよく見るやつがコレ。
一般的にバーベキュー用の炭として売られているほとんどがこの炭だと思います。
100円均一でも見かけるようになりました。入手が簡単で安価な為、初心者は使いがちですが、下記の特徴からあまりオススメしません。


特徴
- 火付きがいい
- 燃焼時間が短い(1~2時間)
- 炎や煙が出やすい
- 爆ぜやすい
- 安価
火付きがよく、短時間でサクッと楽しみたいならこの炭。
軽く舞いやすい、小さな炭が燃えきらなくて消火が面倒。



僕は、形が不揃いでレイアウトが組みにくく、再利用しにくいのでほとんど使いません。
炭代も割り勘に含めて、1回のBBQで使い切りと割り切ってる場合などは利用することもありますが。
黒炭


マングローブ炭と違い、形が均一で放射状の切れ目が入っている。
ホームセンターで切炭などがよく売られている。
特徴
- 火付きがいい
- 燃焼時間は2~3時間
- 煙の出やすさマングローブ炭より少ない
- 形が均一でレイアウトし易い
火持ちがよく、形がととのっているので火力のコントロールがし易い。
その分、マングローブ炭より高価。
白炭


いわゆる備長炭。炭素純度が高く、叩くとキーンという音がします。
ホームセンターでは手に入りにくく、料理屋で利用されることが多い。
特徴
- 火付きが悪い
- 燃焼時間が長い(6~8時間)
- 入手しにくい
- 高価
オガ成形炭


オガクズなどを混ぜ合わせ、型にハメて成形して作った炭。
色んな形に成形できて、豆炭やチクワ型が一般的。
着火材を練り込んだ物や備長炭の特徴に似せた物など様々。
特徴
- 製品ごとに特徴が異なる
- 形が均一でレイアウトしやすい
- 入手しやすい
- 比較的安価
オススメの炭は【オガ炭備長炭】
個人的には備長炭の特徴を模した【オガ炭備長炭】がオススメ。
マングローブ炭や黒炭と比べると火付きは悪いが、火起こし器を利用して放置しておくだけで着火するので、その間に他のBBQの準備をすれば効率的。
一度火が付くと最後まで継ぎ足しなしで楽しめてレイアウトも作りやすいので、どんなグリルでも火力調整が簡単。
燃えきると細かな灰だけになるので捨てるのが簡単。
燃えきっていない炭は崩れにくいので火消し壺に入れて再利用しやすい。
- 火付きが悪い(火起こし器でカバー)
- 燃焼時間が長い(4~6時間)
- レイアウトが簡単
- 入手しやすい
- コスパがいい
BBQを何回もやるのであればかなりオススメです。
僕自身、BBQを初めてからほとんどオガ炭備長炭を利用しています。
火起こし方法【オススメは火起こし器】


今後もバーベキューをする場合、火起こし器を利用することをオススメします。
火起こし器の使い方はとっても簡単。
- 火起こし器に炭を入れる。
- 着火剤に火をつける。
- 火のついた着火剤の上に火起こし器をのせる。
後は待つだけで簡単に火が起こせます。
待っている間に料理の準備ができるのでとっても効率的!
火起こし器が無くても炭の組み方次第で火の起こしやすさはかわってきます。
ここでは簡単にその方法をお伝えします。
その前に・・・
僕は固形の着火材を強くオススメしています。
液体着火材は思わぬ方向に垂れていく危険性や、禁止されていますが継ぎ足ししようとして燃え広がり事故になったという話もききます。
着火材の代わりに新聞紙を利用することもできますが、風の強い日や扇ぎ方によっては灰が舞い散る危険がありますのであまりオススメしていません。
オススメの着火剤はコチラ。


天然素材で嫌なニオイが出ない約1.5cm角のキューブ型着火剤です。
マッチと一体式になったファイヤーライターズも定番でオススメなのですが、こちらの商品は火種は別で必要な分お安くなっています。
ファイヤーライターズが20本で600円台後半、こちらのWeberのライターブロックスは48個と倍以上入って900円台後半で買えます。
万が一火が消えた際に火種が無いと困るので別でライターやマッチ等の火種はどうせ持っているので、そういった意味でもファイヤーライターズのメリットが薄れているのかも。
100円均一で充填式のイワタニのガスマッチが買えるので1本持っておくといいと思います。
ということで、上記を意識して火起こしをしていきます。
炭の組み方
- グリルのロストル(炭を置く部分)に固形の着火材を設置
- 着火材のを囲うように炭を置いていく(井形やピラミッド型)
- 着火材に火をつける
グリルの空気穴の数、燃焼性能によって異なりますがこれだけで火起こしが完了します。
火付きが悪いと感じたらうちわで扇ぎましょう。
炭のレイアウト
強火~弱火保温ゾーン確保
炭に火が付いたらグリルに並べていきますが、全体に均一に並べるのはNG!
BBQは焼くペースも食べるペースも人それぞれ。グリル全面を焼き場にしてしまうと保温スペースの確保ができず食材が黒焦げになってしまいます。
また、野菜など食材やレシピによっては遠火でじっくり調理する方が美味しいものもあるので最低でも炭のある場所、無い場所の2か所は作りましょう。
強火ゾーン→遠火ゾーン→保温ゾーンと炭の高さを段々と減らしていきます。


僕がよくやるのは炭を置くのはグリルの半分まで。それ以降は遠火と保温ゾーンにしています。半分でもグリルの2/3くらいまでは十分熱が届きますからね。
まとめ


今回はバーベキューで使う炭の4種の比較と火起こしについてのご紹介でした。
バーベキュー初心者が最初につまづくポイントが火起こしだと思います。
火起こしに失敗するとその先の工程へ進めず中々バーベキューを楽しむことができません。僕は本格的にバーベキューを始めようとしてから初めて彼女を連れて行ったバーベキューで火起こしに失敗している経験から、火起こしには少し敏感になっているところもあるかもしれませんが。
今回の記事を読んで、誰もが最初から簡単に火起こしをできるようになってほしいと思い執筆しました。
一方で、キャンプの現地で松ぼっくりや枯れ葉を拾ってきて麻紐をほぐしてメタルマッチで火をつける、なんて作業もキャンプでは味があって楽しいイベントの一つだと思っています。
バーベキューで食事や調理を楽しむということに重きを置いた場合は、楽に火起こしができてた方がいいなーというのが僕が長年バーベキューをやってきて辿り着いた考えです。
ということで、お役に立てたら幸いです!今後も皆さん良いアウトドアライフを!またねー。
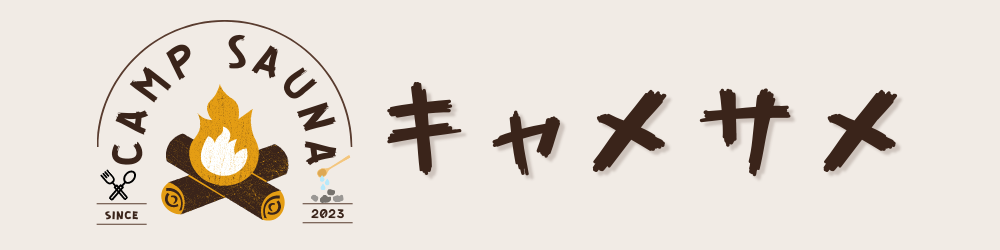
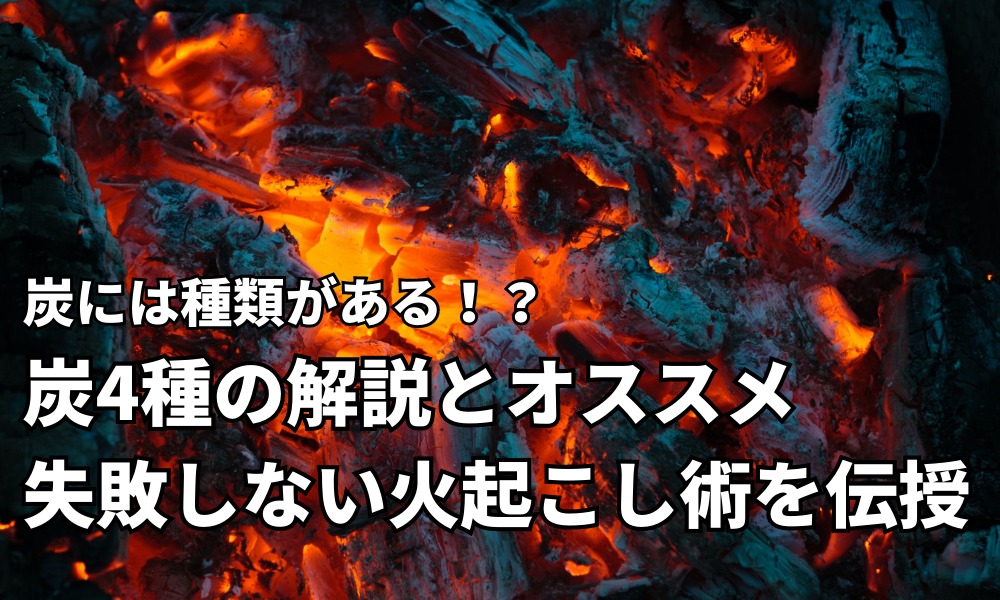




コメント